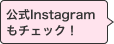一戸建ての固定資産税はいくらかかるの?
敷地面積や築年数によって異なりますが、一般的な目安としては、一戸建てにかかる固定資産税の相場は、年間で平均15万円前後とされています。固定資産税とは、土地と建物のそれぞれにかかる税金で、1月1日時点で土地や建物を所有している人に納税義務があります。
固定資産税は、土地や建物を所有している限り、避けられないランニングコストです。(ただし、一定の基準に満たない土地・家屋・償却資産については課税されません)。また、土地は市況、建物は経年で価値が変動するため、固定資産税額は一定ではなく3年に1度変わります。そのため、あらかじめ税額を把握して、月々の資金計画に組み込んでおくことが大切です。

固定資産税の基本を確認しよう!
固定資産税は、土地や建物などの固定資産にかかる税のことです。まずは、固定資産税はいつ、どこに納税するのかを見ていきましょう。
いつから納税するもの?
固定資産税の納税時期は市区町村によって異なりますが、固定資産を所有した日の翌年の4月頃から始まることが一般的です。固定資産税は1月1日時点での所有者に対して、その年の1年間分が課税されます。そのため、1月2日に所有したら、その翌年の1年間分が課税されることになります。ただし、年の途中で所有者が変わった場合は、所有したタイミングを加味してもとの所有者と新しい所有者との間で税負担の割合を調整して精算するのが通例です。たとえば売買によって所有者が変わったなら、売主と買主が相談のうえ、税負担の割合を決めます。
どこに納税するの?
固定資産税の納税先は、固定資産の所在する市町村(東京23区は東京都)です。固定資産税の納税義務者には、市町村(東京23区は東京都)から納税通知書が送付されます。それに記載された納付期限や税額の通りに、納める必要があります。
滞納するとどうなる?
固定資産税を滞納すると、延滞金が発生します。滞納した分だけ納税額が増えてしまうため、注意が必要です。延滞金は以下の割合で加算されます(2021年以前の延滞分については、お住まいの自治体にご確認ください)。
| 期間 | 2025年1月1日〜2025年12月31日に納税するべき税金 |
|---|---|
| 納税期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 2.4% |
| 納税期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 | 8.7% |
納税期限をすぎても固定資産税が納付されない場合、自治体から督促状が送付されます。催促状が発送されてから10日たつと、自治体が滞納者の財産を差し押さえることが可能になるため、期日を守って納税しましょう。納税におけるそのほかの注意点は後ほど解説します。
なお、固定資産税のおおまかな相場は分かっても、実際にかかる税金はその固定資産の置かれている状況によって違いがあります。たとえば住宅の場合、建物や土地の広さが同じでも、地域や建築資材、周辺地域の地価などによって固定資産税は変わります。
一戸建ての固定資産税をいくらか把握するには?
固定資産税の納税額を把握する方法は、主に4つあります。それぞれ見てみましょう。
- 家屋調査を待つ
- 納税通知書を見る
- 最寄りの自治体で調べる
- 自分で算出する
(各項目をタップすると、詳細にジャンプします。)
家屋調査を待つ
購入を検討している新築住宅の固定資産税額を知りたい場合は、家屋調査での評価を待つのがよいでしょう。家屋調査とは、不動産の評価額を決定するために自治体が行う調査で、専門の調査員が家屋を外観から内装、建設設備に至るまで調査していきます。主に木造と木造以外の構造で評価額が決定され、屋根や柱、壁などがそれぞれ評点の対象となり、固定資産税評価額が決まります。
なお、家屋調査の対象は新築住宅のみのため、2年目以降は、一定のルールにもとづき建物の経年劣化が固定資産税評価額に反映されます。

納税通知書を見る
既に所有している住宅の固定資産税をいくら払うかは、毎年の年度初めに市町村(東京23区は東京都)から郵送される納税通知書で確認できます。ただし、記載が間違っていたり、固定資産税評価額が高く設定されていたりする恐れもあるので、税額に間違いがないか自分で確認するようにしましょう。
最寄りの自治体で調べる
具体的な税額を知るには最寄りの自治体で調べる方法もおすすめです。固定資産税の標準税率は全国一律で1.4%ですが、必要がある場合、自治体は個別に固定資産税の税率を定めることができます。また、自然災害による損害を受けた場合に減免している場合があります。自治体で確認するには、固定資産税台帳を閲覧するか、固定資産評価証明書を発行してもらいましょう。
固定資産税台帳には土地や建物などの評価額が記載されており、納税義務者のほか借地人や借家人等が市区町村の役所で閲覧できます。固定資産評価証明書では評価額を確認できますが、取得できるのは所有者、相続人などに限られているため、身分証明書や必要書類を事前に用意しておきましょう。

自分で算出する
不動産会社や自治体に頼らず、自分で税額を算出する方法もあります。固定資産税は、土地と建物それぞれの評価額の目安を把握し、それに税率をかけることでおおよその固定資産税額を調べることができます。
土地の評価額は、固定資産税路線価に土地の面積をかけることで算出できます。路線価とは、路線に面した住宅の1㎡あたりの評価額のことです。なお、固定資産税路線価は、相続税や贈与税を決定する相続税路線価とは異なることに注意が必要です。固定資産税路線価は全国地価マップより確認できます。建物の評価額は、新築当初は請負工事金額の50~60%程度が目安となります。
一戸建ての固定資産税の計算方法
一戸建ての固定資産税は、自分で計算できます。おおよその税額をつかんでおくと、納税通知書や自治体で調べて提示された額に対する納得度も高くなるでしょう。固定資産税を計算するには主に以下2つのステップを踏みます。

[ 1 ] 固定資産税評価額(課税標準額)を知る
固定資産税評価額と課税評価額は基本的に同一額になりますが、軽減措置がなされた場合は変わります。固定資産税評価額とは、建物の固定資産税を出す際に用いられるもので、各自治体が不動産の価値を評価して計算した価額のことです。土地の価値は変動することがあり、建物も年数とともに劣化するため、固定資産税評価額は3年に1度評価替えが行われます。
では、固定資産税評価額は、どのようにして決まるのでしょうか?固定資産税評価額の算出方法を見てみましょう。
土地
土地の固定資産税評価額の計算式は、「固定資産税路線価 × 面積 × 補正率」となります。固定資産税路線価とは路線に面した住宅の1㎡当たりに対する評価額のことで、補正率とは土地の形状や奥行きに応じた価値を数値で表したもののことです。
建物
建物の固定資産税評価額は、新築か中古かによって変わります。新築の場合は「単位当たり再建築費評点×経年減点補正率×床面積×評点1点当たりの価格」で計算されます。再建築費評点とは、一般的な家屋に使用される資材や設備に設定された点数のことで、経年減点補正率は、家屋が年数の経過とともに生じる損耗状況による減価率のことです。評点1点当たりの価格とは、評点当たりに定められた価格のことを指します。
一方、中古の場合の計算式は「基準年度の前年度の再建築価格×再建築費評点補正率×経年減点補正率×床面積×評点1点当たりの価格」です。再建築費評点補正率は、前回の評価替えからの3年間における工事原価に相当する物価変動の割合から算出されます。
なお、建物の固定資産税評価額は、築年数の経過によって新築時の固定資産税評価額から最大で2割まで下がります。
[ 2 ] 軽減措置で固定資産税を軽減する
軽減措置を利用できる場合は、求めた額から軽減できる分を引くことで最終的な固定資産税の額を求めることができます。
一戸建ての固定資産税を軽減する方法は?
固定資産税は、家にかかるランニングコストのなかでも大きなものです。ただし、固定資産税には軽減措置があり、適用されると減税が可能です。ここからは減税につながる軽減措置だけでなく、知っておくことで税額を抑えられるコツについても解説していきます。

軽減措置を活用する
土地と建物にはそれぞれに軽減措置があります。詳しくは以下の通りです。
土地※1
土地への固定資産税を抑える手段として、住宅用地の軽減措置特例があります。これが適用された場合、税額は以下のように軽減されます。
| 小規模住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき200㎡までの部分 | 価格×1/6 | |
|---|---|---|---|
| 一般住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき200㎡超かつ家屋の床面積の10倍までの部分 | 価格×1/3 | |
たとえば、敷地面積が300㎡の場合、200㎡までの部分は小規模住宅用地の特例が適用され、残りの100㎡の部分は一般住宅用地の特例が適用されることになります。
建物
建物にかかる固定資産税における軽減措置は以下の通りです。
・ 新築住宅に対する軽減措置※2
| 住宅 | 固定資産税額の軽減措置 | 期間 |
|---|---|---|
| 1戸当たりの課税床面積が50㎡以上(貸家40㎡以上)280㎡以下であること | 1/2 | 新築から3年間 |
| 上記条件に加え3階建て以上の中高層耐火建築物 | 1/2 | 新築から5年間 |
いずれも減額の対象となるのは、住宅として使用する部分の床面積のうち、120㎡までの部分となります。また、住宅として使用する部分の床面積が、全体の床面積の2分の1以上であることが必要です。この軽減措置は2026年3月31日までが適用期限です。なお、土砂災害特別警戒区域等の区域内に建設された一定の住宅は、軽減措置の対象外となるため注意しましょう。
・ 新築の認定長期優良住宅に対する軽減措置※3
認定長期優良住宅とは、劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新性、バリアフリー対策、省エネ対策などが講じられている住宅のことです。認定長期優良住宅の認定を受けた住宅の軽減措置は以下の通りです。
| 住宅 | 固定資産税額の軽減措置 | 期間 |
|---|---|---|
| 1戸当たりの課税床面積が50㎡以上(貸家40㎡以上)280㎡以下であること | 1/2 | 新築から5年間 |
| 上記条件に加え3階建て以上の中高層耐火建築物 | 1/2 | 新築から7年間 |
いずれも減額の対象となるのは、住宅として使用する部分の床面積のうち、120㎡までの部分となります。また、住宅として使用する部分の床面積が、全体の床面積の2分の1以上であることが必要です。新築の翌年1月31日までに申告する必要があり、適用期限は2026年3月31日までとなります。
・ 改修工事に対する軽減措置※4※5※6
耐震やバリアフリー、省エネなどの改修工事を行うと、家屋にかかる固定資産税の税額を抑えられる場合があります。減税の対象は工事完了の年の翌年分で、これらの改修工事に伴う軽減措置は、2026年3月31日までとなります。
詳しい内容については国土交通省の税制改正概要をご覧ください。
上記のほか、災害に遭った地域は自治体ごとに減免・軽減措置が適用される場合もあるので、チェックしてみましょう。また、これらの軽減措置は自動で適用されるわけではなく、申請する必要がある点にご注意ください。

新築時の家屋調査には立ち会う
家屋調査を受ける際は、なるべく立ち会って確認するようにしましょう。立ち会いの時間が確保できない場合、書類のみの審査になるため、家の構造や設備を一方的に判断された結果、課税標準額が高くなってしまうこともあります。また、立ち会いの前に固定資産税の相場を知っておくと、家屋調査員と直接話して税額の理由を確認できるでしょう。
固定資産税路線価を把握する
土地の固定資産税路線価の相場も把握しておくことをおすすめします。これをもとに固定資産税額の概算を行ったうえで、固定資産税納税通知書と照らし合わせるとよいでしょう。不明点があった場合はお近くの都道府県税事務所に問い合わせて確認すれば、余計な税を払わずに済むため安心です。
課税額をチェックする
課税額が周辺に比べて極端に高くなっていないか、自治体の固定資産台帳でチェックすることもできます。万が一間違いがあっても、自分から申し出なければそのままの税額が請求される恐れがあります。課税相場を確認し課税額に納得できない場合は、納税通知書の交付から3か月以内であれば、固定資産評価審査申出制度によって再審査の申し出を行うことが可能です。

一戸建てとマンションの固定資産税額は違う?
ここで、一戸建てとマンションの固定資産税を比較してみましょう。建物にかかる固定資産税は、一戸建てよりマンションのほうが高くなる傾向にあります。なぜなら、マンションは鉄筋コンクリート造のものが多く、木造が多い一戸建てよりも建築費が高く、耐用年数も長いためです。
耐用年数とは、対象の建物の資産価値がなくなるまでの期間のことです。会計上の木造の耐用年数は22年、鉄筋コンクリート造の耐用年数は47年とされています。
なお、新築住宅に対する固定資産税の軽減措置を受けられる期間は、一戸建てよりマンションのほうが長いのですが、マンションはそもそもの固定資産税が高いため、どちらのほうが固定資産税を多く引かれるのか一概にはいえません。

新築と中古の固定資産税額は違う?
次に、新築と中古の一戸建ての固定資産税についても比較してみましょう。土地に対する税額は変わりませんが、建物に対する税額は異なります。新築一戸建ての場合は3年、一定の要件を満たせば特例を受けることが可能です。たとえば、一般的な新築一戸建ての場合、床面積が120㎡以下の部分に対して、3年間固定資産税が2分の1になります。
一方で、中古の場合は古くなればなるほど安くなり、木造の場合は築27年程度で下限に達します。実際に新築と中古の一戸建ての固定資産税をシミュレーションしてみましょう。
新築:評価額が2,000万円程度の場合
今回は、以下のような設定でシミュレーションをします。
- 土地の評価額 1,000万円
- 建物の評価額 1,300万円
- 土地面積 200㎡以下
- 床面積 120㎡以下
まずは新築一戸建ての固定資産税のシミュレーションを行います。この場合、土地面積が200㎡以下なので土地に対して「小規模住宅用地の特例」が適用されます。また、家屋が新築の一戸建てかつ床面積が120㎡以下なので、これも併せて特例を受けることができます。そのため、以下のようになります。
| 土地の固定資産税 | 1,000万円(土地の評価額)×1/6(小規模住宅用地の特例)×1.4% | 2万3,333円 | |
|---|---|---|---|
| 建物の固定資産税 | 1,300万円(建物の評価額)×1/2(一般的な新築一戸建ての特例)×1.4% | 9万1,000円 | |
| 実際に納税する固定資産税 | 2万3,333円(土地の固定資産税) + 9万1,000円(建物の固定資産税) | 11万4,333円 | |
中古:評価額が2,000万円程度の場合
一方で、中古の一戸建ての場合は建物に対する特例を受けることができないため、下記のようになります。
| 土地の固定資産税 | 1,000万円(土地の評価額)×1/6(小規模住宅用地の特例)×1.4% | 2万3,333円 | |
|---|---|---|---|
| 建物の固定資産税 | 1,300万円(建物の評価額)×1.4% | 18万2,000円 | |
| 実際に納税する固定資産税 | 2万3,333円(土地の固定資産税) + 18万2,000円(家屋の固定資産税) | 20万5,333円 | |
固定資産税を納税する際の注意点
固定資産税について正しく理解できていても、実際の納税がきちんと行われないとトラブルになってしまいます。そこで、ここでは実際に納税する際に気を付けたいポイントをご紹介します。

納税通知書にもとづいて納税を行おう
納税は、自分で算出した固定資産税額で行うのではなく、納税通知書にもとづいて行いましょう。納税通知書は、4月~6月頃に自宅に届きます。納税通知書が届いたら、書面を確認し納付書を用いて納税しましょう。
納税は年4回の分割払い、または一括払いで行うことができ、納付期限が決められています。期限を1日でもすぎてしまうと、延滞金が加算されるので、必ず納付書の納付期限を確認するようにしましょう。
自分に合った納税方法を選ぶ
固定資産税の納税方法は複数のなかから選択できます。最近では、現金での納税だけでなく、口座振替を使った自動でできる納税や電子マネーなど、さまざまな納税方法があります。主な納税方法は以下の通りです。
- 現金による納税
- ペイジーによる納税
- 口座振替による自動納税
- クレジットカードによる納税
納付漏れや月々のマネープランへの影響がないよう、自分に合った納税方法を選びましょう。
固定資産税がいくらかかるかを把握して、賢く節税を行おう!
ここまで一戸建ての固定資産税についてお伝えしてきました。固定資産税は、不動産を所有している限り毎年納税する義務があります。固定資産税額は、毎年送られてくる納税通知書や最寄りの自治体で調べる方法だけでなく、自分で計算して求めることも可能です。
自分で固定資産税額を求めることで、自分の所有する不動産が特例を受けられるかどうかを確認することもできます。受けられる特例をうまく活用して節税につなげましょう!
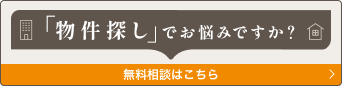

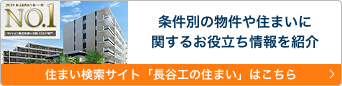
※1出典:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/kotei_tosi.html#ko_02_12
(最終確認日:2025年11月4日)
※2出典:国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000021.html
(最終確認日:2025年11月4日)
※3出典:国土交通省「認定長期優良住宅に関する特例措置」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000022.html
(最終確認日:2025年11月4日)
※4出典:国土交通省「耐震改修に係る固定資産税の減税措置」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000833388.pdf
(最終確認日:2025年11月4日)
※5出典:国土交通省「令和6年度国土交通省税制改正概要」
https://www.mlit.go.jp/page/content/001712685.pdf
(最終確認日:2025年11月4日)
※6出典:国土交通省「省エネ改修に係る固定資産税の減額措置」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001756030.pdf
(最終確認日:2025年11月4日)