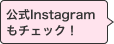布団の収納にはコツがある
まず、収納場所には布団を立てて収納するのがコツです。加えて、湿気対策としては、天日干しのほか、布団乾燥機を使用したり、収納場所に「すのこ板」を敷いたりすることが挙げられます。また、上手な収納のためには必要以上に布団を持ち過ぎていないか、数の見直しも大切ですよ。
布団の収納に困った場合は、大きく分けて2つの方法で解決できます。1つ目は「収納の仕方を変える」、2つ目は「収納する布団の量を適正量にする」、といった方法です。
最近、布団はしまい込むものではなく、季節ごとに入れ替えるものとなり、布団の収納はより可動性の高いものへと変化しています。

布団の収納方法(毎日の場合)
毎日布団を敷いて寝る場合、日常使いの布団の収納は何よりも「出し入れが簡単なこと」が重要です。コンパクト収納を意識し過ぎて出し入れがしにくくなると、布団をしまうのが面倒になり、やがて出しっぱなしになってしまうことも…。
こういった事態を防ぐため、スムーズに出し入れできる布団収納のコツについて紹介します。
押入れに収納するなら上の段にしまう
押入れがある和室を寝室にしている場合は、押入れを利用して布団を収納するのがおすすめです。押入れを活用する際に押さえておきたいポイントは、「高さ・奥行きで空間を仕切る」こと。押入れの高さは上の段と下の段に、奥行きは手前と奥に分けられ、それぞれ収納しやすいものが異なります。
布団の収納に適しているのは、押入れの上の段です。目から腰の高さにある上の段は、「ゴールデンゾーン」と呼ばれます。かがまずに出し入れできるため、頻繁に出し入れするものの収納に適しています。
上の段に、二つ折りにした布団を平置きすれば、必要最低限のアクションで出し入れできます。このとき、布団を折った「輪」の部分を手前にして収納するのがポイントです。輪を手前にするだけで、より取り出しやすくなりますよ。また、重い敷布団は下に、軽い掛け布団は上に重ねるとよいでしょう。そうすることで湿気がこもったり傷んだりするのを防げます。
なお、押入れの下段に布団を収納する場合は、湿気に注意しましょう。布団を収納する際の湿気対策は後ほど詳しく解説します。

クローゼットに収納するなら縦置きがベスト
クローゼットの奥行きは45~60cmが一般的ですが、シングルサイズの敷布団を三つ折りにした場合の奥行きは60cm。そのため、上手に布団を収納するには、平置きよりも縦置きで収納するのがおすすめです。クローゼットは高さを生かした収納を意識するとスペースを有効に使えますよ。
布団を立てるときは、クローゼットの奥行きに合った布団収納ケースを使うと立てやすくなります。また、突っ張り棒をクローゼットの中に突っ張らせることで、布団が倒れるのを防ぐという方法もおすすめです。
倒れにくいマットレスタイプの敷布団であれば、そのまま縦に収納しましょう。なかでも、四つ折りにできるタイプを使えば、奥行きのないクローゼットでも気にせずに収納できます。
このように、クローゼットの奥行きに合わせて収納方法を考えることで、上手な収納になりますよ。
押入れとクローゼット、どちらにしても、毎日使う布団は湿気対策が重要です。人間は、睡眠時にコップ一杯分の汗をかくといわれているため、気付かない間に布団が汗を吸収してしまいます。布団を収納する前の湿気対策についてはこの後、詳しく説明します。

布団の収納方法(普段使っていない場合)
ここまで、普段使いをする布団の収納方法についてお伝えしてきました。では、シーズンオフの寝具や来客用の布団は、どのように収納したらよいのでしょうか?
使用頻度の低い布団を収納する際のポイントは、「かさばらない畳み方」「普段使わないスペースの有効活用」の2点です。これらのポイントを踏まえて、普段使わない布団の収納方法を詳しく見ていきましょう。
布団収納グッズを活用する
すぐ使わない布団を収納するときは、なるべくかさばらないように畳んで収納するのがポイントです。その場合、圧縮袋や収納ケース、収納棚が役立ちます。それぞれの特徴を順に見ていきましょう。
圧縮袋
綿の布団は復元性が高いので、圧縮袋を利用しても問題ありません。一方、羽毛布団の場合は圧縮袋に入れるとボリュームが戻らなくなってしまうため、綿や不織布など、通気性のよい素材の布団用ケースに入れましょう。

収納ケース
収納ケースは、立てて収納できる四角いタイプがおすすめです。収納ケースを購入する際は、押入れやクローゼットの寸法をあらかじめ測っておきましょう。
収納ケースのなかでも、持ち手が付いているタイプなら、奥まったスペースからでも引き出しやすく便利ですよ。

収納棚(伸縮棚、ラック)
押入れやクローゼットの中に、収納棚を置くことでもスペースを有効活用しやすくなります。収納棚を選ぶ際は、キャスター付きで動かしやすいものや、底面がすのこ状になっていて通気性のよいものが、布団の収納に適していておすすめです。
また、ちょうどよいサイズの棚がない場合は、自分で作ってしまうのも選択肢の1つです。布団の重みで棚が落ちてしまわないよう、耐久性や安全性には注意して作ってくださいね。


デッドスペースに収納する
ウォークインクローゼットの奥や、クローゼットの折れ戸が重なる部分は、普段利用することのないデッドスペース。布団をくるくる巻いてベルトを使って留め、縦に置けば、このデッドスペースを有効活用できます。
また、先ほど紹介した圧縮袋を使って布団を薄くすれば、ソファの裏やベッドの下などに隠して収納でき、部屋のスペースを取ることもありません。

素材や色を統一して見た目をスッキリさせる
圧縮袋や収納ケースの素材・色を統一させることで、視覚から入ってくる情報量が整理され、収納スペースがよりスッキリとします。ものの量・場所の把握や管理がしやすくなりますよ。
扉のないクローゼットの場合は、収納グッズの素材や色を家具や壁紙と統一することで、おしゃれでまとまった印象の部屋になるでしょう。
布団の収納袋のおすすめは?選ぶポイント
布団を収納する際に、布団用の収納袋を使う方も多いのではないでしょうか?布団収納袋は商品によっていくつか特徴があり、具体例として以下のようなものが挙げられます。
| 布団の収納袋のタイプ例 | 特徴 |
|---|---|
| 縦置き型 | 自立していてしまいやすい |
| クッション型 | クッションとしてインテリアになる |
| 円筒型 | デッドスペースにしまいやすい |
| バッグ型 | 持ち運びできる |
| 炭入り | 消臭効果が期待できる |
縦置き型の布団収納袋を選ぶときは、袋自体が自立できるものを選ぶと押入れの中で崩れないため、しまいやすく、おすすめです。また、近年では布団を入れるとソファやクッションとして使える収納袋もあります。カラーや素材も複数あり、おしゃれなデザインのものも多いため、どうしても収納スペースが足りない場合は、このようなケースを使ってリビングに置くことも手段の1つです。
加えて、円筒型であれば押入れのデッドスペースに収納しやすく、バッグ型の布団収納袋は取っ手が付いているため、持ち運びしやすいという特徴があります。炭入りの布団収納袋であれば消臭効果があるため、長期的に布団を押入れにしまうシーズンオフのタイミングに活用するとよいでしょう。

布団および関連用品の収納方法とは?
ここまでは、布団を収納する方法を紹介してきましたが、シーツやカバーなどの関連用品の収納も併せて見直しましょう。「一緒に使うものは同じ場所にしまう」のが、収納の基本ルールの1つです。このルールを踏まえ、関連用品を含めた収納方法を紹介します。
押入れにはラックと引き出し収納を利用する
押入れにベッドカバーやシーツを収納するなら、コの字ラックを利用しましょう。
コの字ラックは空間を上下に区切ることができるので、押入れの高さを無駄なく利用するにはとても便利です。コの字ラックの上に布団を重ね、下には引き出し収納を設置してカバー類を収めると、一緒に使うものを1か所にまとめられます。
高さ30cmほどの深い引き出しなら、畳んだシーツやボックスカバーなどを立てて入れられるので、平置きよりもたくさん入りますよ。
写真のように、コの字ラックと引き出しの間には隙間ができるので、布団の通気性が保たれるのも大きなメリットですね。

布団用ケースの中にまとめる
寝具とカバー類など、布団と一緒に使うものはできるだけ1か所にまとめると、家事動線が整って家事がラクになります。来客用布団を収納するときは、来客用シーツとカバーも布団用ケースの中に併せて収納しておきましょう。
それによってシーツやカバーを別の収納場所から取り出す手間が省け、1つの布団用ケースを開けるだけで、1組の布団一式を用意できるようになります。また、シーツやカバーを収納する際に清潔にしてから収納することも重要です。羽毛布団や敷布団は家で洗濯できないものがほとんどですが、布団シーツやカバーなどの洗濯できるものは、収納する前に洗っておくことも長く使うためのポイントになりますよ。

ラベリング管理する
布団用ケースには、「家族用」「来客用」「冬物・夏物」などのラベリングをしておきましょう。ラベリングをすることで、家族全員が一目で中身を判別できます。また、収納スペースや収納ケースにラベリングすることは、「ものを元に戻す」という定位置管理にも役立ちます。ラベルを貼りにくい素材のケースなら、ネームタグ(荷札)を利用するとよいでしょう。
布団を収納する前におすすめの湿気・カビ対策
収納する際には布団の湿気対策をすることも非常に重要です。なぜなら、布団にとって湿気は大敵だからです。布団自体と、収納スペースの中をしっかり除湿しないと、すぐにカビが生えてしまいます。布団を収納する前に、効果的な除湿方法について知っておきましょう。

押入れの下の段では布団を浮かせる工夫をする
押入れの下の段に布団を収納する場合は、湿気に注意しましょう。押入れの下の段には湿気がたまりやすいため、布団にダニやカビが発生しやすくなります。そのため、防虫対策として、「すのこ板」を敷いたり、突っ張り棒を使用したりして布団を浮かせる工夫をしましょう。また湿気対策として、押入れの中を定期的に掃除することも効果的ですよ。
加えて、出し入れの負担を軽減する方法として、キャスター付きの布団収納ラックを活用し、下の段にまとめて収納するといった方法もあります。
天日干しする
天日干しは、湿気のほか防ダニや臭い対策にも役立ちます。綿か合繊の布団なら、週1~2回は外で干すと効果的です。午前10時~午後3時頃までの間で、夏なら1~2時間、冬なら3時間前後を目安としましょう。干している間、一度裏返すと両面しっかりと湿気を飛ばせますよ。
ちなみに、羽毛布団や羊毛布団の場合は、外で長時間干すと劣化の原因になってしまいます。そのため、月2回、1時間程度を目安に行うとよいでしょう。

布団乾燥機を使う
花粉シーズンや梅雨時で布団が干せない、仕事の都合で週末しか干す日がないといった場合には、布団乾燥機が役立ちます。タイプによっては靴や小物の乾燥にも使えるので、ライフスタイルに合いそうなら購入を検討してみるとよいでしょう。

収納スペースの湿気を飛ばす
収納スペースの風通しをよくすることも大切です。扉を閉め切ったままにせず、毎日1時間くらいは扉を開けておきましょう。その際、扇風機で風を送るか、除湿機を使うとより効果的です。
また、空気の入れ替えに加えて、収納スペースに適度な隙間を空けることも重要です。布団以外の衣類などをパンパンに詰め込み過ぎると、通気が悪くなるので、不用品は定期的に整理しましょう。なお、布団を必要以上に持ち過ぎている場合は、この後お伝えする適正量を参考に適宜処分しましょう。

収納時もラクになる!布団の適正量は夏冬1枚ずつ
快適な収納を実現させるためには、持ちものを整理することが大切です。家や収納空間には、物理的に入る量=持てる量が限られているため、その量を超えてしまうと、収納スペースを上手に活用できません。そのため、布団の適正量を意識し不要なものは処分することが重要です。ここからは、布団の適正量を判断するコツを紹介します。

1人1組が基本
必要な布団の枚数は、1人1組、掛け布団は夏冬1枚ずつが基本です。一度、ご自身の持っている布団を全て出してみて、本当に必要なのか見直してみましょう。加えて、シーツや枕カバーは捨て時が分からず、意外と増えてしまうアイテムです。そこで、シーツや枕カバーは収納する前に傷んでいないか、擦り切れていないかをよくチェックして、収納するものと処分するものに分けましょう。
また普段使わない来客用の布団は、家で管理するのではなく、外で保管する方法があります。最近は、布団クリーニングの預かりサービスや宅配型のトランクルームといったサービスがあるので、来客時以外は預かってもらうのもよいでしょう。布団の保管をアウトソーシングすると、収納スペース問題が一気に解決しますよ。
使っていないものは手放してスペースを確保
何年も使っていない来客用の布団といった、この先も使う予定がなさそうな布団は思い切って手放す、もしくは今使っているものと交換してみるなど、「ただ持っているだけ」の状態から卒業しましょう。
処分は面倒かもしれませんが、貴重な収納スペースを無駄遣いしていると暮らしにくくなってしまうため、使っていないものは、手放すようにしましょう。

1つ増えたら1つ手放す
布団のほか、毛布やタオルケットなどもいつの間にか増えていることが多いアイテムです。新しいものが1つ増えたら、古くなったものを1つ手放しましょう。意識して適正量を保つことが、収納スペースをスッキリさせるための大切なポイントです。
寿命を過ぎた布団も処分を検討する
一般的に、掛け布団の寿命は約5年、敷布団の寿命は約3年といわれています。羽毛布団なら、おおよそ5年おきに仕立て直しや、クリーニングすることをおすすめします。寿命を過ぎた布団があれば、すみやかに手放しましょう。寿命を過ぎた布団は、目には見えないカビやダニを多く含んでいる可能性があるほか、汚れの蓄積で布団自体が膨らみにくくなっていることもあります。
なお、処分する場合は、各自治体で定められた方法だけでなく、不用品回収業者に依頼するといった方法もあります。また、新しい布団に買い替える場合は、販売店で引き取ってもらえるケースもあるでしょう。

使用頻度に合わせて使いやすい収納に
布団の収納は、日常使いの布団と、そうでない布団とで収納方法・場所が異なります。毎日使う布団の収納は、暮らしや家事の負担とならないように「出し入れしやすく」を心がけましょう。使用頻度に合わせた収納を意識することで、動線が改善され収納スペースも有効に使えることを、ぜひ覚えておいてくださいね。
また、収納前には、布団に付いているほこりやゴミをきれいに落としたり、しっかり天日干しをしたりといったメンテナンスが重要です。布団収納にひと手間をかけることが、快適な睡眠にもつながります。加えて、整理を先延ばしにしてしまいがちなシーズンオフの布団や来客用の布団は、思い切って預かりサービスを活用してみるのもよいでしょう。整理整頓の手順や持続する収納術を知りたい方は、以下の記事も参考に、住みやすく、使いやすい収納にしてくださいね。
長谷工アーベストでは、収納スペースが広い新築分譲マンション・一戸建てを全国で多数取り扱っております。気になる方は、ぜひ以下のサイトからご覧になってみはいかがでしょうか?
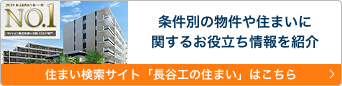
(撮影協力:今井 知加)