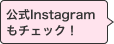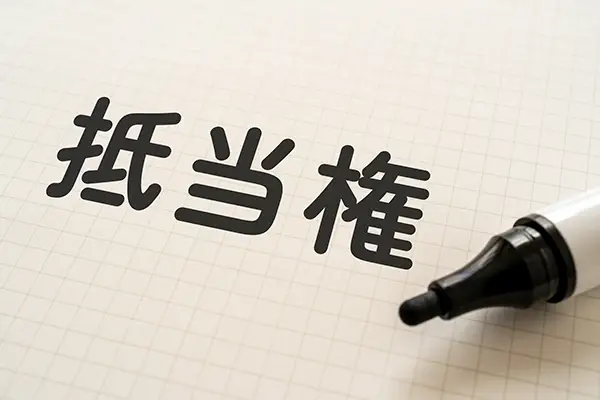抵当権とは
抵当権とは、債権者である金融機関が土地や建物などの不動産を担保にして、債権者が担保物件から優先的に弁済を受けることができる権利のことです。住宅ローンの返済が滞ったときのために、あらかじめ土地や建物を担保としておくものとなります。そのため、住宅ローンを組むにあたり、金融機関から宅地や家に抵当権の設定を求められます。
住宅ローンを組むには抵当権の設定をするのが一般的ですが、抵当権の設定がない特殊な住宅ローンもあります。ただし、無担保住宅ローンは借入可能額が少なく、融資期間も短いほか、金利も高いため特殊なケースを除いては利用しません。

【抵当権】ローンの返済が滞ると、不動産が差し押さえられる
万が一、月々のローンが払えなくなると、抵当権が実行され、担保の家や土地は差し押さえられる場合があります。
差し押さえまでの流れは、3か月以上住宅ローンを延滞すると、督促状が届き、半年延滞すると、金融機関がいつ抵当権を実行してもおかしくない状況になります。
ただし、抵当権が実行されても、競売が申し立てられ、競売が実行されて引渡しが行われるまで、9か月程度かかるため、その間は住み続けられます。つまり、住宅ローンを滞納した時点からカウントすれば、競売の引渡しまで約一年半程度住み続けることが可能といえるのです。
また、住宅ローンを全て返済することが難しいが、競売にかけられたくないという場合は、「任意売却」という手段で売却することも可能です。任意売却の場合、金融機関の了承を得たうえで、競売以外の売却方法により、住宅ローンの完済ができない不動産の抵当権を外してもらうことができます。住宅ローン残債が売却価格よりも高くなっている「オーバーローン」の状態でも、選択できる場合もあります。ただし、競売または任意売却にかかわらず、売却額を充てても残ってしまったローンは、引き続き返済する必要があるので注意しなくてはなりません。
住宅ローンの返済が難しい場合のそのほかの対策として、住宅ローンの借り換えを検討するのもよいでしょう。借り換えによって、以前に借りていた住宅ローンよりも金利を下げられる場合があり、家計の負担軽減にもつながります。

根抵当権との違い
根抵当権(ねていとうけん)は、抵当権と混同しやすいのですが、性質も用途も異なり、家を購入する際には関係がありません。
根抵当権とは、主に融資を受ける企業が利用するもので、「極度額」という金額の限度を定めて、その範囲でお金を借りられる抵当権です。企業は年中、金融機関から融資を受け、そして返済しています。そこで、毎回抵当権を設定したり、抹消したりするのが面倒なため設定するのが根抵当権です。

抵当権に関する手続きを自分でする際の費用
抵当権は、設定や、内容の変更、抹消などをするときにそれぞれ証書の作成・手続きが必要になり、手続きには費用が発生します。ここでは、どのような手続きが必要で、どれくらいの費用がかかるのかを解説していきます。

登記手続き
家の抵当権を設定するには、本人か本人の代理が法務局に出向いて、登記手続きをしなければなりません。登記とは、不動産や所有者に関する情報を登記簿謄本と呼ばれる帳簿に記録することです。多くの場合は司法書士が本人の代理として書類の作成をし、法務局で手続きを行います。
では、登記手続きにかかる費用を詳しく見ていきましょう。
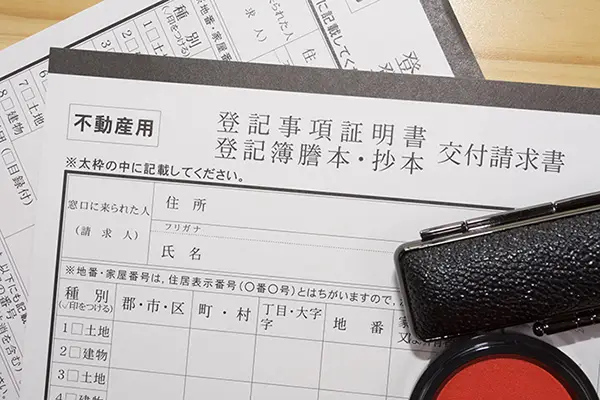
登録免許税
抵当権の設定登記をする際には、登録免許税という税金がかかります。登録免許税は、原則として債権額×税率(0.1%)です。登録免許税については、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひチェックしてください。
印紙代
「金銭消費貸借契約書」に貼り付ける印紙代は、契約書が扱う金額によって異なります。住宅ローンとして借りた金額が、500万円を超え1,000万円以下だと1万円、1,000万円を超え5,000万円だと2万円※1です。
司法書士への報酬
登記手続きを司法書士に依頼した場合は、司法書士への報酬も必要になります。司法書士によって報酬の金額はそれぞれ異なるため、いくつかの司法書士事務所から見積もりを取って、相場を知るのがよいでしょう。
費用目安としては、2万円から10万円と幅広く、たとえば、1,000万円の抵当権を設定する場合、最低でも4万円前後は必要です。司法書士の支払いには、報酬のほかに、交通費用や出張費用など実費がかかることもあります。
雑費
上で紹介した費用のほかに、書類作成に費用がかかります。抵当物件所有者の印鑑証明書の発行手数料は1通300円で、抵当権設定完了後、登記簿謄本を取得したい場合には、1通600円で登記事項証明書の発行が可能です。不動産1つに対し1通なので、家と土地の2つの登記簿謄本を取得するには2通必要となり、1,200円となります。
登記の変更手続き
住宅ローンを返済中に、名義人の変更や住所の移転、住宅ローンの利息など、当初登記した内容と状況が変わることがあります。その場合は、登記内容の変更手続きをしなければいけません。
登記内容を変更する前に、登記簿謄本の内容を確認しておく必要があります。登記簿謄本は、法務局から取得できる書類で、一般的に「登記事項証明書」といわれています。主な記載内容は不動産や所有者に関する情報です。変更前の状況を明確に把握しておくことで、手続きがスムーズに進むでしょう。
また、登記手続きで名義人を変更するに際は、所有権移転登記をしなければなりません。所有権移転登記とは、不動産の所有権が新たな所有者に移ったことを明確にする手続きのことです。
なお、抵当権抹消の登記手続きにかかる手数料は、物件1件の証書につき1,000円で、土地と建物の2つを登記する場合は、2,000円です。こちらの手続きも司法書士に依頼できます。

抹消手続き
住宅ローンの支払いを終えても、登記簿謄本の抵当権の記載は自然に消滅しません。支払いが終了したら、登記を解除する「抹消登記」の手続きを忘れずに行いましょう。
抹消の手続きをしておかないと、登記上では抵当権が付いたままになり、家を売るときや、ほかのローンを組むときの障害となります。
登記の抹消手続きにかかる費用は、法務局への申請料金と、司法書士へ依頼する費用の2つです。法務局への申請料金は、不動産1件の証書につき1,000円なので、土地と建物の両方では2,000円になります。司法書士の費用は、司法書士事務所によってまちまちですが、およそ1万5,000円程度が必要です。ただし、必要書類を用意すれば、司法書士に依頼しなくても自分でも手続きを行うことが可能です。
抵当権抹消を自分でする際の手順
抵当権抹消手続きを自分でするときの流れは、以下の通りです。
- 金融機関より送られてきた抵当権に関する書類を確認
- 管轄の法務局を調べる
- 必要書類をそろえる
- 法務局もしくは法務局の公式サイトから登記申請書を入手し、記入
- 法務局へ申請する
- 完了
抵当権抹消手続きを自分で行う際、登記申請書はオンラインで簡単に用意できます。そのほかの抵当権抹消手続きに関する必要書類は以下の通りです。
- 弁済証書
- 登記済証(もしくは登記識別情報)
- 登記事項証明書
- 委任状
上記は金融機関から住宅ローン完済後に送られてきます。抵当権抹消手続きを自分で行うのか、金融機関が用意した司法書士に費用を出して任せるのかの確認書類も含まれています。自分で手続きを行う際は、その旨を手紙できちんと返信しましょう。
抵当権の付いた不動産の売買や相続は可能?
家を購入するときに設定する抵当権ですが、時間がたち、家を売ったり相続したりするときも、その抵当権が残っていることもあります。
抵当権の付いた不動産は売買や相続ができますが、注意が必要です。どのような点に注意が必要なのかをお伝えします。

抵当権付きの不動産を購入する際には注意が必要
不動産に抵当権が付いていたとしても、理論上、売買することは可能です。ただし、抵当権付きのままの物件を購入した場合、かつての売主が住宅ローンを滞納すると、購入後の家が競売にかけられます。
そのため、抵当権付きの物件は、抵当権を抹消した状態で購入することが絶対条件です。一般的に抵当権付きの物件は、引渡しと同時に抵当権の抹消を行います。売主は、買主の支払った代金を銀行へ返済することで住宅ローン残債を完済して抵当権の抹消を行うのです。
通常、不動産会社が仲介に入る住宅の売買では、抵当権の抹消は必ず行われますので、ご安心ください。
仮に不動産会社の仲介を入れず、個人間で売買をする場合は、抵当権の抹消を購入の条件とすることが必要です。
家を購入するときには住宅ローンの状況や購入にかかる諸費用、必要な手続きを事前に確認し、トラブルなくスムーズに進められるよう準備しておきましょう。

相続する物件に抵当権がある場合は放棄もできる
相続した家や土地などの不動産に抵当権が付いていた、という場合、2通りの事情が考えられます。
1つは、事実上のローン返済は終わっているのに、登記上の抹消登録をしていない場合です。この場合は、特に気にせず相続して、抹消登録手続きをしましょう。
もう1つは、ローンの返済を終えずに亡くなったというパターンです。被相続人(亡くなった人)が団体信用生命保険に加入していれば、死亡時に住宅ローンの完済が行われます。仮に、被相続人が団体信用生命保険に加入しておらず、引き続き返済を行わなければならない場合は、相続人が住宅ローン残債も相続します。
もし、住宅を売却しても住宅ローンが完済できない場合、相続放棄という選択肢も考えられます。
相続放棄は、「相続の開始を知ったときから3か月以内」に行うことが必要です。ただし、相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになるため、ほかのプラスの財産も含めて全て相続できなくなります。
相続放棄は最終手段です。原則としては、引き継いで売却し、ローンの完済をしましょう。

以上、抵当権についてご紹介しましたが、言葉の意味や手続き、費用などお分かりいただけたでしょうか?住宅ローンを完済したら、抵当権の抹消手続きを忘れずに行いましょう!
よくある質問【抵当権】
最後に、抵当権について実際に役立ちそうなポイントを質問形式でまとめてみたので、ぜひ参考にしてくださいね。
登記手続きを自分でするとき、書類に不備があったらどうなる?
登記申請後の審査で何かしらの不備が発生した場合、法務局から補正を求められます。補正内容が多く、補正に時間がかかる場合には、申請を一度取り下げることも可能ですが、結果的に新しく書き直すほうが早く終わるケースもあるので柔軟に対応しましょう。
抹消手続きを自分でするのが不安な場合、どうすればいい?
法務局では抵当権抹消に必要な登記の手続きについて、予約制で事前相談を実施しています。電話や対面などで申請書の記載方法を説明してくれます。登記手続きをどうしても自分で行いたい方や、不安な方は利用してみるとよいでしょう。
ただし、法的な決断・アドバイスは相談対象外です。そのため、登記申請後の審査で追加の申請事項や費用、修正などが生じることもあり、書類の不備が完全になくなることを確約するものではありません。加えて、代理人が手続きをする場合は、事前相談であっても委任状が必須なため注意が必要です。
事前相談を何度も利用することになったり、抵当権抹消の手続きが難しいと感じたりした場合は、司法書士への依頼を検討しましょう。
抵当権が付いていても売買できる?
抵当権付きの不動産を売却するには、ローンの残債を返済し、抵当権抹消手続きをする必要があります。
不動産会社が仲介に入る住宅の売買であれば、抵当権の抹消は必ず行われるため購入者は不動産購入の際に抵当権の有無について、心配する必要はないでしょう。個人間売買の場合には、購入者は抵当権抹消をすることを購入の条件とする必要があります。
※1出典:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
(最終確認日:2024年8月6日)