マンション購入ガイド
![]()
マイホーム購入の要点を解説!
マイホームの購入を考え始めています。購入するには物件の代金以外にどのくらいの費用がかかるものなのでしょうか?また、購入資金はどのように準備しているのでしょうか?併せて、マイホームを購入する人たちの年齢層や収入は一般的にどのくらいなのかも教えてください。
マイホームの購入にかかる諸費用は購入する物件や資金計画によって異なるので、一概にお伝えできませんが、マイホームの購入資金については住宅ローンを利用して購入する人が多くなっています。国土交通省が公表している令和2年度住宅市場動向調査書では、マイホームを購入する年齢層は30代が最多です。世帯年収に関しては、400万〜600万円未満の層が最多となっています。
情報提供:不動産コンサルタント 秋津 智幸
目次
マイホームを購入する人の傾向は?
「いつかは自分の家を持ちたいな…」と、マイホームへの憧れを持つ人は多いのではないでしょうか?マイホームを購入すれば、その家が自分の資産になり、賃貸住宅と違って好きな間取りやデザインにリフォームできるなど、多くのメリットがあります。
しかし、いざ購入しようとなると、「どれくらいの費用があればよいのだろう?」「いつ買うのがベストなんだろう?」と疑問や不安が出てきますよね。
今回は、マイホームの購入を考え始めた人の参考になるよう、購入した人の年代や年収の状況、購入時の費用がどうなっているのかをお伝えします。また、スムーズに家を購入できるように知っておきたい、購入の流れについてもご紹介しますよ。ぜひ参考にしてみてください。
●マイホームを購入するメリットに関する記事はこちら

マイホームを買うと「資産」ができることについて詳しくご紹介しています。

購入した年代は30代が最も多い
国土交通省が実施した2020年度の調査によると、新築注文住宅・新築一戸建て・新築分譲マンションのいずれも、購入した人は30歳代が最も多い結果となっています。新築注文住宅40.9%、新築一戸建て46.1%、新築分譲マンション約35.8%と、いずれも40%前後が30代の購入でした。※1
購入のタイミングは人それぞれですが、一般的には結婚、出産、子どもの入進学、子どもの独立など、家族のライフステージが変化するタイミングが多いようです。特に結婚や出産、子どもの入進学などライフイベントの多い30代にマイホームを購入する人が多く見られます。

初めて購入した世帯の年収は400万円~600万円が多い
同じ国土交通省の調査データでは、新築建売または分譲のマイホームを購入した世帯の収入を見ると、特に初めて購入した世帯主(一次取得者)で40歳未満では、世帯年収400万円未満が3.2%、400万円~600万円未満が34.9%となっています。※1
マイホーム購入の際、なかには住宅ローンを組まずに全額自己資金で購入する人もいます。全額自己資金で購入する場合は、住宅ローンを組む場合と異なり、住宅ローンの利息や、借り受け時の融資手数料、金融機関による抵当権設定登記費用などの諸経費のほか、ローン利用にかかわる時間と手間も節約することができます。
●マンションの現金購入に関する記事はこちら
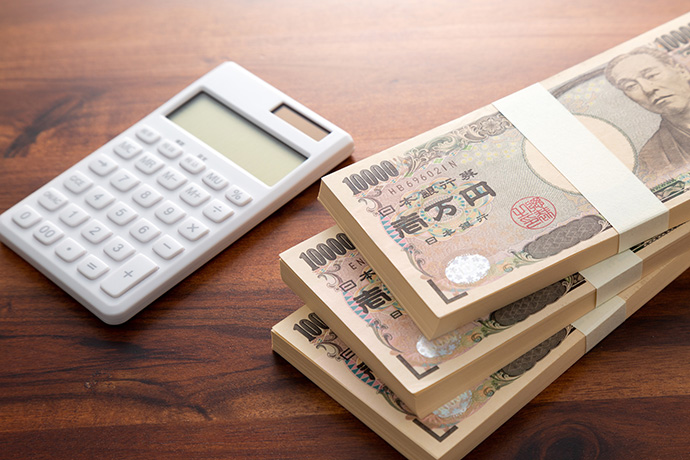
マンションを現金一括で購入するメリットと注意点について詳しく紹介しています。
住宅ローンを利用して購入する人が多い
同じ国土交通省の調査データによると、新築戸建て住宅を購入した人の67.7%、新築分譲マンションを購入した人の62.6%が住宅ローンを利用しています。
●住宅ローンに関する記事はこちら

住宅ローン控除についてご紹介しています。
マイホーム購入というとハードルが高いように感じてしまうかもしれませんが、数値で見ると高年収でなくとも住宅ローンを利用してマイホームを購入している人が多いことが分かります。ここ数年は過去最低水準の低金利が続いているため、住宅ローンは比較的利用しやすい状況になっていることがマイホーム購入の後押しする要因のひとつとなっているようです。
住宅ローンを利用するには収入以外の要件もありますが、毎月ある程度の安定した収入がある人ならば住宅ローンを利用しやすく、マイホームを購入できるということですね。
また、現在の住宅ローンは金利が低く利用しやすいというだけでなく、「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」と呼ばれる税制上の特例措置が用意されています。

マイホームの選択肢
マイホームを購入する際に、マンションか一戸建てか、新築か中古かは、非常に迷うところですよね。そこで、これらの特徴を比較しながらご紹介していきます。
マンションと一戸建て
マンションは、一戸建てと比べて、次のような特徴があります。
・駅から徒歩圏に建てられていることが多い
・建物が鉄筋コンクリート造のような構造で耐震性や防火性能が高い
・土地の権利をマンションの所有者で共有するため、同じ立地なら比較的安く購入できる
また、そのほか一般的な分譲マンションであれば、ゴミ出しは24時間所定のスペースに出すことができたり、宅配ロッカーなどの共用施設があったりします。マンションによってはゲストルームやキッズルーム、トレーニングジムなどといった特別な共用施設を活用できるというところもあります。こうした戸建てにはない共用施設があるのもマンションのメリットです。
加えて、建物の構造上、気密性が高いことや共用部分にはオートロックや防犯カメラなどのセキュリティ設備が充実していることもマンションのメリットといえます。
一方、一戸建てはマンションと比べて以下のようなメリットがあります。
・土地の権利を自分や家族だけにできる
・建物の増改築やリフォームを自由にできる
・建物の建て替えも自分の判断でできる
・自由にペットの飼育ができる
また、独立した建物であるため、プライバシーを保ちやすく、足音や生活音が原因のご近所トラブルが起こりにくい傾向にあります。また、敷地内に庭や駐車スペースが確保されている一戸建てなら、自由に庭造りすることができ、駐車場代がかからず玄関を出てすぐに車の乗り降りができる点もメリットといえますね。ほかにも、管理費や修繕積立金といった費用を月々支払う必要がないというメリットもあります。
●住宅購入に関する記事はこちら

マンションや一戸建てのメリットや注意点などの特徴を比較して解説しています。
新築と中古
新築は、誰も使ったことがないきれいな内装で設備も新しく、耐震性や高断熱性、省エネ性など最新の住宅性能を持つ物件が多いのが嬉しい点です。また、購入時の登録免許税や購入後の固定資産税といった税金で優遇措置を受けることができるのも新築のメリットといえます。
ただし、立地や建物の構造、面積などが同水準の家で比較すると、中古に比べて価格が高くなります。また、新築マンションや新築一戸建ての建売住宅は、希望するエリアに新築の売り物件が出るとは限らないので、希望する立地に購入できる可能性が限定的になります。
一方、中古は新築に比べて、立地や建物の構造、面積などが同水準の家なら価格は安くなる傾向があり、住みたいエリアを絞って探しても予算的には比較的見つけやすい傾向があります。また、未完成の新築マンションや新築の建売一戸建てを購入するのと比べると、実際の建物を確認してから購入できるので、納得して購入しやすいというメリットもあります。
ただし、新築に比べると設備は古くなってしまい、築年数が古い住宅の場合は住宅性能が低い物件である可能性があります。ですが、リフォームやリノベーションを施すことで、見た目がきれいになるだけでなく、最新の設備を導入することもでき、自分好みの生活空間を作り出すことは可能です。

マイホーム購入にかかる費用は?
欲しいマイホームについてイメージできたら、次に気になるのは費用面ではないでしょうか?マイホームの購入時や購入後にどんな費用が必要になるのか住宅ローンを利用する場合で少し詳しくご紹介します。
初期費用
住宅を購入する際には、頭金のほか、諸費用も必要です。詳しく見ていきましょう。
●頭金
頭金とは、購入物件代金のうちの住宅ローン以外に支払う自己資金の部分のことです。自己資金に余裕がある場合には、頭金をどのくらいの金額用意するのかは自分で決めることができます。頭金を多く用意できれば、その分、住宅ローンの借入額を抑えることができ、毎月の返済額も抑えることができます。
一般的に、頭金は購入する物件価格の20%を用意しておくのが理想といわれます。たとえば、購入する物件の価格が4000万円であれば、頭金が800万なら理想的といえるでしょう。
もちろん、物件価格の20%以上の頭金を用意することもできますし、逆に頭金をなしにして、物件価格と同額の住宅ローンを利用することもできます。住宅ローンを利用する際は、毎月の返済額が無理のない範囲となる借入金額で収まるよう、可能な範囲で頭金を用意するとよいでしょう。
●頭金を決めるポイントに関する記事はこちら

住宅ローンを組む際、頭金を設定するポイントについてご紹介しています。
●諸費用
マイホームを購入する際は、頭金だけでなく、諸費用も現金で用意しておく必要があります。代表的な諸費用として以下のものが挙げられます。
・登記費用(所有権移転登記、抵当権設定登記など)
・契約用の印紙代(売買契約、金銭消費貸借契約(ローン契約))
・固定資産税・都市計画税の清算金
・住宅ローンを利用する金融機関の融資手数料
・中古の場合は、不動産会社へ支払う仲介手数料
・中古マンションの場合、管理費、修繕積立金の清算金
・新築マンションの場合、修繕積立基金など
・火災保険料
こうした諸費用の目安は、新築のマンションや一戸建ての場合は物件価格の4~6%程度といわれています。中古住宅では、これらの諸経費に仲介手数料が加わるため、物件価格の7%~9%程度と見ておくとよいでしょう。

購入後にかかる費用
住宅ローンを利用する場合、当然ながらマイホーム購入後には、毎月、住宅ローンの支払いが始まります。住宅ローン以外にかかる費用についてもきちんと計算しておき、毎月の生活費を圧迫しないように、自分の収入に合ったローンの返済額や返済方法を考えておくことが大切です。一般的にマイホーム購入後には主に以下のような費用がかかります。
・不動産取得税(購入後、1回だけ)
・固定資産税・都市計画税
・マンションの場合は管理費や修繕積立金
・ケーブルテレビの設備費用
など
不動産を購入した後、しばらくすると「不動産取得税」の支払いがあります。市区町村によって納付(請求)する時期にはバラつきがあり、数か月から遅いところで1年程度後になります。ただし、自宅を取得した場合には土地建物それぞれに税金を計算するうえでの軽減措置が設けられています。
また、毎年1月1日時点の所有者に対して、所有している土地と建物に「固定資産税」が課税されます。そのほか、都市計画区域内では「都市計画税」という税金も課税されます。なお、固定資産税と都市計画税は同時に徴収されることが一般的です。
特にマンションの場合は毎月、マンションの管理費・修繕積立金も必要になります。通常マンションの築年数が経つにつれ、管理費や修繕積立金は高くなっていくので、将来、支払う金額が増えることも意識しましょう。さらにマンションであれば、ケーブルテレビなどの設備費、駐車場や駐輪場の使用料、専用庭やルーフバルコニーの使用料といったものも発生します。
一戸建てを購入する場合は、毎月の管理費や修繕積立金は不要です。しかし、自分で建物の維持・管理をするため、不具合が起こった場合はその都度費用が発生することになるので、自分で蓄えておく必要があります。また、一戸建ての場合でもケーブルテレビなど使用する設備によっては毎月かかる費用もあります。
こうした購入後にかかる税金や費用を考慮に入れて、マイホームの資金計画を立てることをおすすめします。
●マンション購入後にかかる費用に関する記事はこちら

マイホームを購入した後、必要になり諸費用や税金についてご紹介しています。

マイホーム購入の流れは?
では次に、マイホームを購入する際の流れについて説明していきましょう。予算を決めて物件を探し、申込み、契約そして引渡しまでのおおまかな流れを見ていきましょう。
[ 1 ] 予算を決める
まず、いくらぐらいのマイホームを購入する(できる)かを決めましょう。このとき、物件の購入に使うことのできる自己資金(頭金と諸費用の合計)を無理のない範囲で決めます。そのうえで、返済に無理のない範囲で借りることのできる住宅ローンの金額の目安を算出します。このように無理のない自己資金と住宅ローンの借入額の合計を、購入する物件の予算としておくことをおすすめします。
そのため、自己資金が少ない場合や借入できる住宅ローンの金額が少ない場合は、希望する住宅の予算に足りないこともあります。住宅ローンがいくら借りれるかについては、金融機関に事前に相談しておくと現実性の高い予算を組むことができます。
[ 2 ] 希望物件を探す
予算が決まったら、物件を探し始めましょう。最初に希望するエリアや立地、家族に合わせた間取り、欲しい設備などの希望条件を決め、その条件に優先順位を付けておきましょう。希望する条件を明確にしてから物件を探すと、理想の物件に出会いやすくなりますよ。
マイホームの購入に際しては、この先10年、20年住んでも後悔しないようによく考えて物件を決めることが大切といえます。特に、周辺環境は変えることができないので、立地についてはよく検討することが重要です。
●マンションを選ぶ方法に関する記事はこちら

マンション選びのポイントについて詳しくご紹介しています。
[ 3 ] 購入物件を決める
インターネットやチラシなどで気になった物件があれば、問い合わせをして新築物件はモデルルーム見学、中古物件は、建物の内覧依頼をしてみましょう。見学に際しては、室内の様子を見学するだけでなく、気になる部分は不動産会社の担当者や中古なら所有者に質問して説明を受けましょう。もちろん、気になる物件をいくつか比較してみることも大切です。
自分の希望条件に合った、あるいは納得できる物件に出会ったら、まずは不動産会社の担当者にその物件を購入する場合の資金計画や住宅ローンのことなどを相談しましょう。相談後、ローンの借り入れや資金計画的にも問題がないという判断ができたら、申し込みを行います。
●モデルルーム見学に関する記事はこちら

モデルルームの見学会について詳しくご紹介しています。
[ 4 ] 購入申し込みを行う
購入の意思が固まったら、中古物件であれば仲介する不動産会社を通して購入の申し込みを書面で行います。新築マンションでは、申込受付の期間がある場合はその期間内に、申込受付期間がない場合はその希望するときに、書面で正式に申し込みをします。
申し込みと同時、またはその前後に、金融機関へ住宅ローンの事前審査をお願いすることが多くなっています。

[ 5 ] 売買契約を交わす
中古物件の場合は、売主と買主双方が条件に納得できれば、売買契約となります。また、新築一戸建ては、建売住宅の場合は中古物件と同様に売主と買主が納得できれば、売買契約となります。特に、新築マンションの場合は、規模の大きなマンションであれば、契約会など決まった期日に売買契約を行うケースもあります。
売買契約に際しては、物件や契約内容についてきちんと確認することが大切です。「重要事項説明書」や「売買契約書」の内容をきちんと読み、理解してから契約するようにしましょう。
なお、新築中古を問わず、売買契約時には手付金として売主へ物件価格の5%~10%程度の金額を支払うことが一般的なので、現金で手付金の準備が必要です。
[ 6 ] 住宅ローン審査の承認を待つ
売買契約を交わした後、住宅ローンの正式な申し込みを行います。事前の審査を通っている場合でも、正式な審査(本審査)で承認が出ないと融資は利用できません。
本審査では売買契約書や重要事項説明書、手付金の領収書などの写しの提出が必要なので、売買契約後に本審査となります。本審査が承認されたら、金融機関と金銭消費貸借契約(ローン契約)を正式に結びます。

[ 7 ] 決済・引渡し
金銭消費貸借契約後、中古物件であれば、売主と買主の日程を調整して物件の決済・引渡しを行います。新築マンションの場合、規模の大きな物件であれば、指定された日程で引渡し会のような形で行われることもあります。一般的には、決済・引渡しでは司法書士が立ち合います。
決済とは、物件の売買代金の残金の支払いやそのほかの費用の支払い、中古物件では税金などの清算金の授受を行うことです。住宅ローンを利用する場合は、決済日当日に必要な書類の確認が行われた後、融資が実行(指定口座へローンの資金が振り込まれる)されます。売主が残代金の入金を確認すると、物件の引渡しとなります。
引渡しは、物件の鍵の授受、所有権の移転をもって行われ、通常、金銭の授受と権利の移転や設定は同日に行います。引渡し時には、所有権の移転登記を行い、同時に住宅ローンの担保として抵当権が設定されます。この所有権移転登記が完了して正式に自分名義のマイホームとなります。
●新築と中古マンションの購入の流れの違いに関する記事はこちら

新築と中古マンションの購入の流れは異なります。それぞれ購入方法とその違いについてご紹介しています。
無理のない資金計画で後悔のないマイホーム購入を!
マイホームの購入は、人生のなかで大きな買い物といえるでしょう。後悔しないために、マイホームの購入を考え始めたら、将来のライフプランもイメージして購入時期や返済計画、立地や間取りなど物件の条件を考えることをおすすめします。
たとえば、将来子どもができたことを想定したり、子どもが独立した場合を考えるなど、先を見据えることで、必要な建物の広さや教育費など将来の生活費まで考慮することができるでしょう。そこから適切な住宅ローンの返済額を想定することで、自分に合った住宅ローンの借入額を設定することができるようになります。
ほかにも、仕事で転勤になる可能性や、将来親の介護が必要になったときなどのことを踏まえたライフプランを想定すれば、物件に対する希望条件も変わってきます。希望する条件が異なれば、当然ながら、マイホームの立地や建物の広さ、間取り、設備などの希望も異なってきますし、それに応じて物件価格も変わってきますから、予算をはじめ資金計画も想定しない場合と変わってきますね。
住宅購入では、できれば自己資金は余裕を持って準備しておくと安心です。ただし、自己資金が少ない場合でも、今は住宅ローンが借りやすいこともあり、購入しやすくなっています。自己資金が少ないときに購入する場合は、何よりも住宅ローンの返済額を、生活に支障のない程度にゆとりのある額となるよう抑えることが大切です。

また、中古物件の場合は、仲介してもらう不動産会社選びも、マイホーム購入を成功させるポイントになりますよ。不動産会社には、マンションや戸建てといった取り扱う物件や取り扱うエリアに得意不得意があります。希望に沿ったマイホーム候補を数多くご紹介してくれるだけでなく、物件周辺のことや住宅ローンのこと、税金のことなどもきちんと説明してもらえる不動産会社や担当者を選ぶようにしましょう。
もし、予算や住宅ローン、住まい選びなどに対してお悩みがあれば、長谷工住まいアドバイザーに無料相談してみましょう。信頼できる住まい選びのプロにお任せして、理想のマイホームを見つけてくださいね!
●長谷工住まいアドバイザーへの無料相談はこちら

住まい探しのプロである長谷工の住まいアドバイザーが物件探しや資金の相談など無料でお受けしています!
※1 出典:令和2年度住宅動向調査,国土交通省
https://www.mlit.go.jp/common/001401319.pdf
(最終確認:2024年11月18日)

情報提供:不動産コンサルタント 秋津 智幸
不動産サポートオフィス 代表コンサルタント。公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士。不動産コンサルタントとして、物件の選び方から資金のことまで、住宅購入に関するコンサルティングを行なう。